古里を求めて
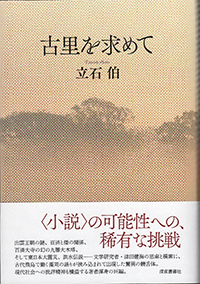
四六判上製/カバー装
発行日:2020/1/9
本文436頁
装幀:高林昭太
定価:3400円+税
ISBN978-4-88032-457-9
立石 伯著
立石 伯(たていし・はく)プロフィール
文芸評論家・作家。1941年8月、鳥取県生れ。法政大学大学院博士課程単位修得後中退。
著書に『埴谷雄高の世界』、『石川淳論』など作家論、作品論など多数。
小社からの刊行著書は、『ドストエフスキィの〈世界意識〉』、『『死靈』の生成と変容――埴谷雄高のヴィジョンと無限の自由』、『随感録』、小説『西行桜外伝』。ほかに小説『朔風』、『玉かづら』等がある。
オビ(表)
〈小説〉の可能性への、稀有な挑戦
出雲王朝の謎、百済と倭の関係、百済大寺の幻の九層大木塔、そして東日本大震災、洪水伝説――文学研究者・津田健海の思索と模索に、古代奈良で働く藻刈の語りが挟み込まれて出現した驚異の饒舌体。現代社会への批評精神も横溢する著者渾身の巨編。
オビ(裏)
最難解、晦渋とされる不世出の作家埴谷雄高『死霊』(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ/講談社文芸文庫)や石川淳『紫苑物語』『焼跡のイエス・善財』(同)の解説等で、批評の〈現在〉を告知してきた文芸評論家、立石伯。
本書『古里を求めて』は、埴谷・石川の継承者たらんとする己が単独者の稀有なる魂の軌跡を鮮烈に刻む初の長編小説。構想十数年、形而上的思索の深淵と覚醒、論じられる側へと決行された転位の偉観を見られたい。
あとがき
本作『古里を求めて』は、個人誌「第2次星雲」のⅠ(2015年9月)からⅢ(2016年10月)まで3回にわたって連載した作品を大幅に改稿した上で成立している。三年近くも間隔があいたのは、『「死靈」の生成と変容』『随感録』(ともに2017年10月深夜叢書社刊行)を上板したために、まとめるのに時間がずれたためである。
かつてこの作品を書くにあたって、いくつか決断したことがある。その第一のものは、近・現代日本の文学(あるいは世界文学の日本語翻訳文学など)が常に探求しつづけてきたいわゆる「文学」「小説」という観念・理念などを基本的な側面では承認するとしても、それらをできるだけ括弧にくくっておくか、一度は払拭してしまおうという意図が秘められている。書く対象、素材なども、これまで小説的・文学的といわれている対象にとらわれぬことにした。書くべき対象は、したがって現代の事柄も、過去の問題も、近未来の予測も、古い時代の事柄も同じ作品空間に同居する。具体的なことと抽象的なこと、現在の政治・社会的な問題や歴史的な出来事などが混融する。夢幻・空想的なものと生々しい出来事が語られたり、あるときにはえんえんたる議論がつづいていくこともある。ドストエフスキイのいくらかの小説のような饒舌体的形式を踏襲してもいる。いわば形式・内容という既成の観念も廃棄する、というよりも尊重しない。言葉、文章を書けばある形をなし、何らかの内容が出現してくるから、それにまかせるしかない。
冒頭の書きだしに作品と書いたが、作品ということではなく、単なる〈書きもの〉として一定の容量のものが作品と称される器に盛られることになる。非文学的、反小説的な一つの試みだといってもよい。小説世界といわれているものが包含していた諸要素をふくめた〈非小説〉的世界というべきものを表現世界に顕現させるということにほかならない。作品についての一般的な判断は書くものの側にはないことを再認識しながら、現在流行の小説と徹底的に遠ざかるとともに、それらに不信を投げかけつづけることになる。
(後略)
解説(栞文15枚から抄出)
可能性としての〈非小説〉を求めて――立石伯『古里を求めて』に寄せて
藤村耕治(法政大学文学部教授)
〝こんな小説、読んだことがない——〟
読中読後の、率直な感慨である。本書を手にした人は、複数の任意のページを開いて、それらの行文を眺めてみてほしい。そこには、歴史に関する独特な知見や、およそ小説らしからぬ言葉による激烈な現代社会批判や、粗野なもの言いをする男の独白などが展開されている。いったいこれは何か。異様である。けれども、これは紛れもない〈小説〉である。読者は、戸惑いつつも読み進めながら、時にその創見に驚き、正鵠を射た批評に頷き、非現実的なイメージに眩惑され、さて読み終わった後、冒頭の言葉を呟くことになるだろう。これは、〈小説〉の可能性への、稀有な挑戦である。
(中略)
(語り手の「わたし」である)健海はこうして、自身の生の古里、故郷や国としての古里、人間存在の源である古里を見出すことになる。つまり、本作における〈古里〉とは、たんに生まれ育った場所をのみ指すのではない。常にそこにあり、そこにない逃水のゆらぎの中の古里、いつでも帰ることができ、そこから飛び立つことを保証してくれる古里、さらにいえば地上にあるとともに宇宙に遍在する古里なのである。それは人間の過去・現在・未来、あるいはその死とその先までを、あらゆるものの生成と消滅の繰り返しの中で、唯一照らしてくれる何かだといえる。
立石伯の4冊目の小説である本作は、氏のこれまでの経験、思考、探求のことごとくを投入し、表出した長篇小説である。そのペンが及ぶ対象は、あまりにも多岐にわたる。ここでは物語の主軸を示すことしかできなかったが、それ以外のモチーフをざっと挙げてみるなら、埴谷雄高・石川淳・坂口安吾・魯迅・ギリシャ哲学者・ランボー・ドストエフスキーなど氏が長年親炙してきた作家・思想家たちの文学的・方法的・思想的な継承、健海とその父親双方に託された氏自身の経歴や体験への省察、近代以降の日本の政治や社会の在り方に関する認識と批判などであり、それらが、延々たる議論や講演記録や論文の挿入といった形で、縦横に繰り広げられる。夢や不可思議な現象、鮮烈なイメージなどがこれらと相接して現れる。このありようを「あとがき」で氏はみずから〈非小説〉的世界の顕現と述べているが、現在小説と呼ばれる殆どのもの、その枠組みに捉われた発想や弛緩した文学精神への異議申し立てに他なるまい。本作が、表現世界における〈小説〉の可能性への稀有の挑戦であると述べた所以である。
