文学的思念の光彩
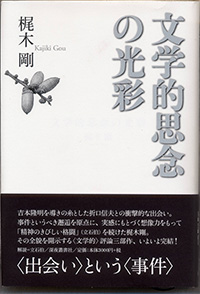
四六判/上製/本文372頁
装丁=高林昭太
発行日:2012/10/25
定価:3000円+税
ISBN978-4-88032-403-6
梶木剛 単行本未収録評論集3
梶木剛(かじき・ごう)プロフィール
文芸評論家。本名、佐藤春夫。1937年5月、新潟市生まれ。1957年、新潟県立新津高等学校卒業、法政大学文学部日本文学科入学。在学中に吉本隆明と出会い、雑誌「試行」に文学評論を発表、以降常連執筆者となる。1962年より千葉県の県立高校に教諭として勤務。1998年に退職後は、弘前学院大学教授、法政大学大学院講師なども務めた。
2010年5月、食道癌による敗血症のため死去。享年73。
主な著書に『古代詩の論理』『斎藤茂吉』『思想的査証』『存在への征旅』『夏目漱石論』『宿命の暗渠』『長塚節』『折口信夫の世界』『柳田國男の思想』『正岡子規』『抒情の行程』『子規の像、茂吉の影』『写生の文学』などがある。
オビ
〈出会い〉という〈事件〉
吉本隆明を導きの糸とした折口信夫との衝撃的な出会い。
事件というべき邂逅を原点に、実感にもとづく想像力をもって
「精神のきびしい格闘」(立石伯)を続けた梶木剛。
その全貌を開示する〈文学的〉評論の三部作、いよいよ完結!
目次
Ⅰ
事件としてのある出会い-折口信夫と吉本隆明
折口信夫のたたかい-文献・歴史実証主義への批判
アジア的、実感、まれびと
神の嫁と神隠し-『死者の書』『遠野物語』『山の人生』
逸脱と還相-吉本隆明『〈信〉の構造』を読む
平野謙戦後初頭
平野謙『志賀直哉とその時代』
Ⅱ
古井由吉の現勢-女性・家・自然
古井由吉『女たちの家』
横光利一の現在
横光利一の評価
横光利一の復権
横光利一の現在性
デニス・キーン『モダニスト横光利一』
菅野昭正『横光利一』
佐々木重治郎ほか『折口信夫を〈読む)』
汲めども尽きぬ折口信夫-西村亨編『折口信夫事典』一読
石内徹『折口信夫』
『「反核」異論』その他
吉本隆明小筆
歳月というもの-八木義徳『風祭』を読む
八木義徳『文学の鬼を志望す』
『奥野健男文学論集』賛
奥野健男『素顔の作家たち』その他
奥野健男『文学のトポロジー』
保昌正夫見渡し
保昌正夫断簡
関口安義『評伝松岡譲』
関口安義編『芥川龍之介研究資料集成』に寄せて
藤井貞和『古日本文学発生論』(増補新装版)
藤井貞和『日本〈小説〉原始』
Ⅲ
徳田秋聾展望-とくに『假装人物』から『縮圖』
還相の思想の一実践-島尾敏雄『死の棘』を読む
司馬遼太郎『峠』再読
人麿の像二、三
月村敏行『幻視の鏡』
芹沢俊介『浮力と自壊』
中上健次『化粧』
立松和平『今も時だ』その他
清水昶『太宰治論』その他
庄野潤三『屋上』
桶谷秀昭『風景と記憶』
中山和子『平野謙論』
古橋信孝『神話・物語の文芸史』
本多秋五あれこれ
梅原稜子『海の回廊』
大谷晃一『与謝蕪村』
河野修一郎『千年の森』
四元仰歌集『石塵』
安田速正『長塚節「鍼の如く」』
短歌新聞社編『大正昭和の歌集』
勝又浩『作家たちの往還』
大星光史『越後の歌びと』
今西幹一スナップ
佐藤志満・全歌集以後
[解説]
実感にもとづく想像力の射程 立石伯
梶木とのこと 佐藤満洲子
書評より(「週刊読書人」2012年12月14日号、抜粋)
力強い背骨を持った膂力の人
田村雅之(詩人・砂子屋書房代表)
膂力の評論家、梶木剛の厖大でかつ重厚な遺稿集が刊行された。
『文学的視線の構図』、『文学的思考の振幅』、『文学的思念の光彩』と題された、あわせると千二百頁を越える、堂々・圧巻の遺稿集である。
没後一周年哀悼出版として出された一巻目は、「文学に関する断片」と題された梶木の尊敬する四人、斎藤茂吉、正岡子規、夏目漱石、柳田國男についての論稿からはじまる。
(中略)
三巻目の『文学的思念の光彩』の巻頭に一葉の写真がある、吉本宅を訪れた折のものらしい。梶木が吉本隆明宅を頻繁に訪ねたのは一九六一年、『試行』創刊時の頃である。
二十六歳、一九六三年に満洲子夫人と結婚、仲人は吉本隆明夫妻であった。
最初の著書は『古代詩の論理』(試行出版部)、二冊目が村上一郎編集の『斎藤茂吉』(紀伊國屋書店)。さきの写真はこの『斎藤茂吉』を届けに行った折と思う。わたしはちょうどその頃、白皙の新人文芸批評家梶木剛と出会うのだ。
三冊目、わたしの編集になる評論集『思想的査証』が一九七一年に出る。
以降、書きに書きまくった梶木剛は十七冊もの著作をものすことになる。遺稿集を合わせると、二十冊に届く。その精緻な探究、徹底した文献の渉猟、暗闇をまさぐるような、腰を落とした筆遣いも特徴だった。
この三冊の遺稿集のなかで、異彩を放つのは、やはり晩年に集中して書き進めた「椿とたぶの木」をめぐる論稿である。
千葉市の梶木宅に見舞いに行った折、わたしは宮崎の銀鏡(しろみ)神楽の話をした。「ししとぎり」という狂言風のものを見たと話したら、突然、その神の杖は椿の木のはずだと、強い調子で言ったのだった。
二巻目の『文学的思考の振幅』の三分の一が「照葉樹林」の稿で占められる。それは究極、折口信夫と柳田國男を視野に入れつつ、稲作文化やタブの木の日本原植生論を包含した照葉樹林の実在を明かし、ついに二人を越えるという壮大なモチーフに溢れている。
(中略)
梶木剛の特徴は、柳田國男と折口信夫の対立ではなく、両者がそれぞれ独自に、また影響を互いに受けつつ、それぞれ論究を深めていった事実を検証し、自らの経緯(ゆくたて)を定めていることだ。ヨーロッパ的な普遍主義に真向うから対立することを思想の本質とする、と繰り返し説きながらである。
この三巻を読むと、梶木剛の出発に、吉本隆明の論文「詩とは何か」(一九六一年、「詩学」七月号)が強烈なものとしてあったことがうかがえる。すべてのはじまりが、吉本隆明の折口信夫絶賛のこの論にあった。三巻の冒頭論考、「事件としてのある出会い――折口信夫と吉本隆明」が書かれる。
(中略)
晩年の吉本隆明の書斎で、「皆が想定しているよりはるかに梶木剛は力強く、いつしか驚嘆するほどの仕事を仕上げる人なのだ」、と吉本がわたしにひとりつぶやくように言ったことを想い返している。膂力の人、背骨の力がしっかりしているのだ。その人が、「驚嘆するほどの仕事」になるはずだった最晩年の論述を、病で中断せざるをえなかったのが、無念だと思う。
